事典の功績
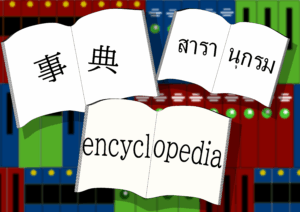
CAS番号(CAS登録番号、CAS registry number、CAS RN®︎)が化合物などの物質の特定に使われている。CASとは、Chemical Abstracts Serviceの頭文字である。2017年から商用目的での使用は有償になっている。同じように物質を特定する番号にECやPubChemがあるが、これらは今のところフリーのようである。しかし、念のため、使う前にチェックしておく方がよいだろう。
かつては、メルク・インデックス(The Merck Index)という重厚な本がよく使われていた。化合物などの百科事典である。物性や構造などの情報が得られる。筆者が学生だったときは、文献に出てきた化合物を、教授室の入り口の本棚にあったメルク・インデックスで調べて、自身の研究にも使えそうか考えたものである。当時はそれが楽しかった。今ではメルク・インデックスはオンライン化されている。膨大な数が収録されており、科学や人類に大きな貢献をしていると思う。
The Merck Index Online (https://merckindex.rsc.org/)
1世紀に古代ローマにいたペダニウス・ディオスコリデスは、薬理学、薬草学の父と言われている。ディオスコリデスは、自身の観察を基に薬物誌(De Materia Medica)を作った。植物薬600種、鉱物90種、動物35種が収められていた。薬物誌は1500年以上、薬学、医学の基礎文献とされたと言われている。また、そのうち100種くらいは、現在でも何らかの用途で使われているようである。先入観にとらわれず、ディオスコリデス自身の観察に重きを置いたことも特徴であり、彼の創作といったニュアンスもあったのかもしれない。
こういった事典の作成では、資料や情報の収集、体系化、目録の作成、文字化、理解を促す図や挿絵など、作業が多い。今日の科学や文明は、様々な事典の作成者、編集者、出版社の支えがあってこそだと、感謝の念を抱く。最近だと生成AIを使うのだろうか(だとしても、個人的には、最終チェックは人がしてほしいと思う)?
追記 (2025年10月6日)
先日、近所の小学生に国語を教えているときに、国語辞典で知らない単語を調べてもらうと、なかなかできない。また、文章を読んでいて、単語などを文字では認識できないが、読んであげると、その意味はわかっている。といったことがおきた。スマホを使って調べる、と言ったので見ていると、音声で入力していて、スマホも人工音声で答えていて、そういうことか、と思った。
