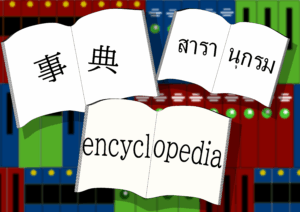DNAとか遺伝とか

DNAは、生物が遺伝情報の保持に用いている物質です。連なっていて、その並び方(配列)に意味があります。すなわち、その配列が遺伝情報です。遺伝情報には、タンパク質の配列を決める情報や、遺伝子発現を制御する配列などが含まれます。しかし、DNA配列の意味について、まだまだわかっていないことが多いです。
1869年に、ヨハネス・フリードリッヒ・ミーシェルは、病院で廃棄される包帯に付着していた膿からリン酸の多い物質を見つけました。これが、記録に残っているDNAの発見です。
1928年にフレデリック・グリフィスは、肺炎双球菌の実験で形質転換を起こす物質(遺伝物質)の存在を示しました。1944年にオズワルド・エイブリー、コリン・マンロ・マクラウド、マクリン・マッカーティが、その物質がDNAであることを明らかにしました。1952年に、アルフレッド・ハーシーとマーサ・チェイスが、ファージの実験で、DNAが遺伝物質であることを裏付けました。
1945年に、フレデリック・サンガーは、タンパク質を構成するアミノ酸の並び順を解析するDNP法を発表しました。サンガーは、タンパク質の機能の理解には、構成されているアミノ酸の種類だけでなく、その技術で明らかになるアミノ酸の配列が重要であると考えたようです。そこから、タンパク質の遺伝情報を担うDNAにも、同じように配列があると推測されました。ほどなくして、DNAの構造が解明され、それに追随する多くの研究から、DNAに配列があることが共通認識になります。そして、DNA配列の解析方法が開発されました。今日では、遺伝情報について、物質としてのDNAではなくDNA配列に意味があることは、常識になっています。
アミノ酸やDNAという”物質”にではなく、それらの”配列”に意味がある、という事実は、生物学を大きく変革させました。自然科学では、より細かくその構成要素を分析することで物事を理解しようとします。上述の通り、生物学も昔は、細胞の中にある”物質”の解析や遺伝を担う”物質”の発見を目指していました。それが、サンガーの功績で、生物の構成要素であるアミノ酸やDNAを”物質”として調べても、生物のことはわからない、ということが認識されました。現在では、生物学研究では、DNA配列が持つ意味の理解や、アミノ酸が連なって高次構造をとっているタンパク質の機能解析が行われます。
生物にとっては、”物質”ではなく”配列”が意味を持つことは、生物学が社会の容認を得ることにも役立ちました。宗教的な話ですが、自然法則は神様が創ったとされていて、化学や物理学は神様の意思を理解する作業とされます。一方で、生き物は神様が設計したものであり、自然法則とは別との意見があります。その考えは、生物を物質として理解しようとしてた昔の生物学研究とは相容れないものでした。しかし、DNAは配列に意味がある、となると、生物学に賛同したようです。なぜなら、配列とは言葉(コード)であり、言葉は神様が創ったものという教義から、言葉で設計されている生物は神様の創造物、と解釈できるからのようです。
話を戻します。サンガーは、1975年にDNA配列の解析方法も開発しています。その功績で1980年に2回目のノーベル化学賞を受賞しています(1回目は、上述のアミノ酸配列解析)。その時の同時受賞者に、ポール・バーグがいます。バーグは、SV40ウイルスのDNAを人為的に組換えることに成功しています(DNA組換え技術は、1973年に、スタンリー・コーエンとハーバード・ボイヤーによって確立されていました)。DNA組換えは、現在では、適切な手続きと設備が整えば、トレーニングされた人なら日常的に行います。遺伝子の機能を調べたり、有用物質を生産するためです。しかし、バーグらの時代では、人為的に遺伝情報を変えることへの恐怖が強かったようです。
DNA組換えの基本操作では、DNAを切る酵素と繋げる酵素を使います。DNAを切るときは、主に制限酵素が使われます。制限酵素は適切な緩衝液の中では決まった配列だけを切る酵素です。同じ制限酵素で切った断片同士はリガーゼなどの酵素で繋げることができます。そのようにして、切断して単離したDNA断片を、任意のDNA配列に組み込むことができます。これまでに、天然(バクテリア)から複数の制限酵素がみつかっています。現在では、DNA断片は必ずしも生物から得る必要はなく、人工合成することが可能です。ギブソン法によるDNA組換えでは、制限酵素が必ずしも必要ではなくなりました。トランスポゾンや相同組換えを利用する方法もあります。このように、DNA組換えの技術は進歩を続けています。
DNA組換え技術は、遺伝情報の研究や社会応用に不可欠です。バーグらは探究心からDNA組換えを行ったと思いますが、周囲から、DNA組換えの危険性に対する警告があったようです。バーグは最初は警告に反発したようですが、警告を聞き入れて研究をストップさせたようです。その頃、容易になったDNA組換え実験の停止を提案するモラトリアム・レターというものが出され、当該分野の研究者は実験を自粛しました。そして、バーグらの呼びかけで、1975年にアシロマ会議が開催されました。そこでは、DNA組換え技術を使うにあたり、どういった取り決めがあった方が良いかが、3日間、約140人の研究者で話し合われたようです。そして、どういった設備が必要か、規制を今後どう変えていくか、といった、気をつけながら使うという方針が決まりました。現在の「予防原則」「順応的管理」も同じです。これは、科学の発展のために科学の問題を科学が解決したと評価されています。科学者の自主規制の良い例となっています。このように科学者が倫理観を保ち、自浄作用を機能させている限り、法規制は最低限で済みます。その結果、変化に柔軟に対応できる仕組みができています。
DNA組換え技術は、それを使う仕組みができて、発展を続けています。基本は、DNAを加工する技術、DNAを増やす技術、DNAを細胞に導入する技術です。当初は加工したDNAを導入する程度でした。導入したDNA配列の影響で形質が変われば成功です。導入したDNAが長期間保持されるような工夫が進み、一方で、DNAの相同組換えやトランスポゾンといった現象が解明されてくると、それらが応用されて外来のDNA断片を細胞のゲノムに組み込むことができるようになりました。これにより、外来DNAが脱落する心配が無くなりました。DNA組換え生物の系統を樹立できるようになりました。
DNA組換え技術が浸透してくると、国際的な新しい取り決めとして、カルタヘナ議定書が交わされました。それでは、遺伝子を組換えた生物の国境を越える移動に焦点を当て、環境への影響の心配がないような措置などが規定されています。アシロマ会議は米国が中心で行われましたが、2023年9月の時点では、米国はカルタヘナ議定書を批准していません。
紀元前に、プラトンは「国家」で、遺伝の仕組みを理解することでそれを自在に扱えるようになる、というようなことを述べています。DNA組換えの技術で、人類はようやくそこに辿り着こうとしています。DNA組換え技術が適切に使われることで、医薬品や酵素など、社会に役立つ製品が作られています。DNA組換えは生物系の研究に欠かせない技術になっています。ルールが遵守され、かつ、透明性の高い研究環境では、従事者や監督者が細心の注意を払っている限り、ほとんど問題は起こらないようになっています。
一方で、社会にはDNA組換えに否定的な声があるのも事実です。しかし、DNA組換え技術を用いた製品は、なんでも流通させてよいわけではなく、安全性や最終製品の純度などが審査され、認められる必要があります。DNA組換え技術を使う人も、それを審査する人も、他者に被害を与えようとしているのではなく、むしろ、よりよい製品を提供するために努力している、ということです。
付録
グラム陰性菌のモデル生物の大腸菌(Escherichia coli)は、DNAや遺伝子の研究にも大きな貢献してきました。DNA組換えは主にプラスミドと呼ばれる環状DNAで行われます。大腸菌はプラスミドを染色体外DNAとして保持、複製できます。しかし、不要な遺伝情報としてプラスミドが大腸菌から脱落することがあります。それを防ぐために、プラスミドに抗生物質耐性遺伝子を組み込んでおき、プラスミドを導入した大腸菌をその抗生物質の存在下で維持します。プラスミドが脱落すると大腸菌は死ぬため、その抗生物質存在下では導入したプラスミドを保持した細胞だけが生存できます(生存している大腸菌=プラスミドを保持している大腸菌)。DNA組換えでは、プラスミドを抽出し、制限酵素で切り、そこにDNA断片を組み込み、大腸菌に導入します。うまく組み込めていると大腸菌の中でそのプラスミドが増やされます。プラスミドは動物細胞に導入することもできます。プラスミドにウイルスの遺伝情報の一部を組み込むと、動物細胞で実験用の安全なウイルスが生産できます(複製能を持たないウイルス粒子、第三世代と呼ばれる)。